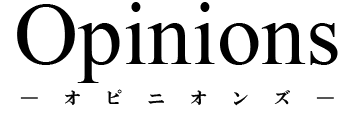- 記事一覧
- ゲストライター記事一覧
- 認知症「早期診断」の「呪い」を解くために:「当事者視点の症候学」へ向けて
認知症「早期診断」の「呪い」を解くために:「当事者視点の症候学」へ向けて

現在「認知症」の早期診断が急速に広まる中で、医療現場ではこれがどういう意味を帯び始めているのか?このような問題意識で「認知症早期発見時代のネオ・ジェロントロジー」と銘打ったシンポジウムを慶應大学で3月に開催したところ、認知症医療を牽引してきた第一線の専門医等が集まった。中でも印象的だったのは、ある医師による発言――「認知症」という診断が現在「呪い」として機能していないか――という問いを、フロアの医師や研究者たちが真摯に受け止め、認知症臨床をどうしたらより救いのあるものにできるか、熱い議論が交わされたことだった。
医療的診断とは、本来ならば当事者の苦悩に言葉を与え、治療の選択肢を示し、予後の見通しを立てることで、人々に希望を与え得るものだ。それが(がんのように)重篤な病であれば尚更のこと、診断は、「その人がその人らしく生きるため」の契機となり得るものだろう。ところが、認知症に関しては、どうも必ずしも上手くいっていないようだ。確かに認知症に関する理解が足りず、虐待や隔離という悲惨な状況が見られた2000年代には、早期診断・早期介入を進めることに大きな意味があった。しかし認知症の啓発が進む中で、逆に「早期診断」が「早期絶望」をもたらしていないか――診断を下したものの適切な支援につながらず、人生をどう立て直していいのか当事者も途方に暮れる、(当事者の藤田和子さん1)がいうところの)「空白の期間」が生じていないか――が問われるようになっている。
1)2007年、45歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断される。NPO法人「若年性認知症問題にとりくむ会・クローバー」副理事長。
早期診断をめぐる混乱の理由として、第一に「科学的不確実性」が挙げられる。「認知症」とは、未だ科学的合意が得られていない複雑な症候群であり、治療法どころか確実な診断法すらも確立されていない。にもかかわらず、早期診断の動きが拡大していくことで、超高齢社会によって要請される社会的入院も含めた、急激な老いの医療化が起こっている。しかし病因論としてのアミロイド仮説2)に対する疑念が強まり、製薬会社も次々と抗認知症薬開発から撤退する中で、人々が抱く医療的救済への期待と、医師が直面する科学的不確実性の乖離はますます大きくなっている。
2)アルツハイマー型認知症の原因として、いま最も支持されている仮説。神経細胞外に老人斑といわれるアミロイドがたまり、脳の萎縮につながると言われている。
第二は、治癒がない中で高まる「予防」への期待だ。認知症の市民講座で最も人気を博するのは「予防」だというが、認知症予防をめぐるメディア言説には、時に奇妙なまでの明るさと、(まるで、ひたすら心身の鍛錬を続ければ認知症から永久に逃れられるかのような)魔術的思考が感じられる。確固たる予防法がまだないにもかかわらず、いたずらに「予防/対策」が謳われることの裏には(認知症を認めて共存する覚悟を決めるというよりは)、「回避/根絶」を願う新たなスティグマ3)さえ感じられる。科学的エビデンスが欠けた脳トレ等を自治体が推奨する中で、逆に不合理な希望と絶望のサイクルが生み出されないかが懸念される。
3)汚名の烙印を押されるといった意味があり、心身の障害や貧困による社会的な不利益や差別、屈辱感や劣等感のことをいう。
第三に、認知症の啓発が進むことで、「正常な老い」へのハードルも高くなってしまっている。少し前までは多少の物忘れは老いの一部として受け取られていたのに対して、現在「正常な老い」を支えてきた家族や地域の基盤が崩れる中で、老いの病理のみに注目が集まりがちだ。特に夫婦仲や家族仲が悪い場合、いつ自分が認知症とラベル化されるか分からないとの不安と疑心暗鬼が生まれ、潜在的な家族間葛藤が顕在化しかねない状況がある。自分はいかに健康で、しっかりしているのかを常にアピールしなくてはいけないような、強迫的な相互監視が生まれるならば、それは何とも生きづらい社会だろう。認知症を免れた人が「健康エリート」として、また予防に失敗した人は健康群からの「脱落者」としてスティグマ化されてしまいかねない中、不幸な老いの階層化を避けるためにはどうしたらいいのだろうか?
このような早期診断の「呪い」を解くために、専門医たちは自ら「当事者性」を帯びた存在として語り始めていることにも注目したい。長谷川式4)で有名な長谷川和夫先生がカミングアウトされたように、認知症になってもできること、認知症だからこそできることを語ること――さらに、藤田さんが指摘するように「不便だけど不幸ではない」日々を、生活者の視点から捉え直す動きが生まれつつある。今回のシンポジウムで基調講演を行った北米の専門家、マーガレット・ロック教授は、日本の認知症医たちがこれほどまでに「生身の患者の思い」に寄り添い、現象の微細さや科学的不確実性に真摯に向き合っていることを高く評価された。現在、臨床現場から生まれつつある医師の自省性と、当事者と協働して作る、当事者の語りを統合した新たな「認知症症候学」が、「呪い」を解く大きな鍵となるかもしれない。
4)「長谷川式簡易知能評価スケール」、認知症の可能性があるかどうかを、簡易的に調べる問診項目のこと。
北中淳子「認知症病前診断時代の医療」『老年精神医学雑誌』29(5)2018参照。
本論の基となる研究は科研費基盤B(JP16H03091)と基盤C(16KT0123)の助成を受けている。
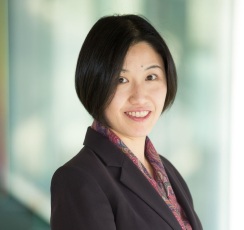
Recently Popular最近よく読まれている記事
-

食べていても痩せる 高齢者終末期のカヘキシア(悪液質)
食べていても痩せる。活発に運動を続けている人なら不思議に思わないが、介護度の高い高齢者にそのようなことが果たして起こるのだろうか。起こるのであれば、それはカヘキシアという病態であれば説明できる。 カヘキシア(悪液質)カヘキシアとは、食欲不振・体重減少・全身衰弱・倦怠感などを呈し、生命予後やQOL(qualit… -

終末期の自然な経過を見極めるとは
長期に渡り胃ろうからの栄養を続けていると、注入した物が食道へ逆流したり、唾液や痰の貯留が増えたりして、吸引を繰り返すことになるが、結局のところ、頻回の吸引も間に合わず、心肺停止状態で発見されることが多い。これでは看取りとは言えない。ここに至るまでの言葉を語れない人の苦しみ。このような事態を避ける智慧… -

自閉症スペクトラムと呼ばれているような障害は、実は障害ではない。生物としての人類のバリエーション(変異)の一つである。
自閉症スペクトラムと呼ばれているような障害は、実は障害ではない。生物としての人類のバリエーション(変異)の一つである。本来は人類の、生息環境に対する適応の一つのあり方だというのが、ニューロダイバーシテイ(脳多様性)という考え方に他ならない(詳しくは正高信男著『ニューロダイバーシテイと発達障害』(北大… -

社会保障分野での普遍主義と選別主義について
介護保険や医療保険では、貧富にかかわらず保険によって9割が給付(自己負担は1割)あるいは、7割が給付(自己負担は3割)される。この様な社会保障の方式は、「普遍主義」といわれている。「普遍主義」は、義務教育や、最近では高等学校の授業料にも適応されている(この場合も裕福な人も貧しい人も同様に無償である)。反… -

飲まず食わず(自発的飲食中止)という選択、VSEDをご存知ですか?
前回(Opinionsで9月24日配信記事)は有馬斉氏による安楽死の分類と、我が国の現状についてお伝えしました。また我が国においては、医師の致死的薬剤の処方による積極的安楽死は、法的に支持されていないということもお話ししました。諸外国では医師による致死的薬剤処方による安楽死が認められている国もありますが、もち… -

医療崩壊
ある日の外来。朝の9時から診察室に座りっぱなしでそろそろ3時間が経過。既に再診患だけではなく、その日の新患も回ってきます。で、そうした中に問題のおじさんがいました。「今、○○クリニックで薬をもらっていまして・・・」「30日分貰っているのですが、お腹が痛くなったので、診てもらいに来ました」「○○先生の紹介…
Writer ライター
-
 受賞作品Opinionsエッセイ
受賞作品OpinionsエッセイOpinionsエッセイの記事を見る
-
 ペンネーム東沖 和季
ペンネーム東沖 和季東沖 和季の記事を見る
-
 ニセコ在住下田 伸一
ニセコ在住下田 伸一下田 伸一の記事を見る
-
 ペンネーム 看護師宇梶 正
ペンネーム 看護師宇梶 正宇梶 正の記事を見る
-
 武蔵野大学大学院大谷 航介
武蔵野大学大学院大谷 航介大谷 航介の記事を見る
-
 一般社団法人村楽東 大史
一般社団法人村楽東 大史東 大史の記事を見る
-
 会社員池松 俊哉
会社員池松 俊哉池松 俊哉の記事を見る
-
 (公財)橋本財団研究助成 成果報告
(公財)橋本財団研究助成 成果報告研究助成 成果報告の記事を見る
-
 横浜市立大学小林 天音
横浜市立大学小林 天音小林 天音の記事を見る
-
 東京西徳洲会病院小児医療センター 小児神経科医師秋谷 進
東京西徳洲会病院小児医療センター 小児神経科医師秋谷 進秋谷 進の記事を見る
-
 公益財団法人地方自治総合研究所 常任研究員坂本 誠
公益財団法人地方自治総合研究所 常任研究員坂本 誠坂本 誠の記事を見る
-
 ペンネームAurora
ペンネームAuroraAuroraの記事を見る
-
 つむぐ株式会社 代表取締役竹村 仁量
つむぐ株式会社 代表取締役竹村 仁量竹村 仁量の記事を見る
-
 岡山大学学術研究院医歯薬学域長谷井 嬢
岡山大学学術研究院医歯薬学域長谷井 嬢長谷井 嬢の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員Karki Shyam Kumar (カルキ シャム クマル)
ソシエタス総合研究所 研究員Karki Shyam Kumar (カルキ シャム クマル)Karki Shyam Kumar (カルキ シャム クマル)の記事を見る
-
 NPO法人妊娠しぇるとSOS 理事長小林 智子
NPO法人妊娠しぇるとSOS 理事長小林 智子小林 智子の記事を見る
-
 書きたい人のためのwebマガジンOpinions編集部
書きたい人のためのwebマガジンOpinions編集部Opinions編集部の記事を見る
-
 介護福祉士渡口 将生
介護福祉士渡口 将生渡口 将生の記事を見る
-
 相談支援専門員・福祉ネイリストゆき
相談支援専門員・福祉ネイリストゆきゆきの記事を見る
-
 株式会社ありがとうファーム取締役副社長馬場 拓郎
株式会社ありがとうファーム取締役副社長馬場 拓郎馬場 拓郎の記事を見る
-
 ジャーナリスト ペンネームジョワキン
ジャーナリスト ペンネームジョワキンジョワキンの記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員Andi Holik Ramdani(アンディ ホリック ラムダニ)
ソシエタス総合研究所 研究員Andi Holik Ramdani(アンディ ホリック ラムダニ)Andi Holik Ramdani(アンディ ホリック ラムダニ)の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員Waode Hanifah Istiqomah(ワオデ ハニファー イスティコマー)
ソシエタス総合研究所 研究員Waode Hanifah Istiqomah(ワオデ ハニファー イスティコマー)Waode Hanifah Istiqomah(ワオデ ハニファー イスティコマー)の記事を見る
-
 元芝園団地自治会岡﨑 広樹
元芝園団地自治会岡﨑 広樹岡﨑 広樹の記事を見る
-
 岡山外語学院留学生カーン エムディ マムン
岡山外語学院留学生カーン エムディ マムンカーン エムディ マムンの記事を見る
-
 行政書士板垣 岳人
行政書士板垣 岳人板垣 岳人の記事を見る
-
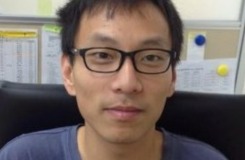 Crimson Education教育コンサルタント蘇 暁辰(Xiaochen Su)
Crimson Education教育コンサルタント蘇 暁辰(Xiaochen Su)蘇 暁辰(Xiaochen Su)の記事を見る
-
 神戸大学准教授斉藤 善久
神戸大学准教授斉藤 善久斉藤 善久の記事を見る
-
 ドイツ在住阿部プッシェル 薫
ドイツ在住阿部プッシェル 薫阿部プッシェル 薫の記事を見る
-
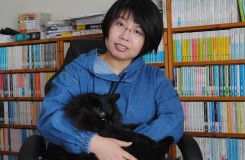 ライター/編集者黒部 麻子
ライター/編集者黒部 麻子黒部 麻子の記事を見る
-
 翻訳家田尻 潤子
翻訳家田尻 潤子田尻 潤子の記事を見る
-
 アブダビ環境庁長官 Environment Agency – Abu Dhabi (ead.gov.ae)シャイカ・サレム・アル・ダヘリ
アブダビ環境庁長官 Environment Agency – Abu Dhabi (ead.gov.ae)シャイカ・サレム・アル・ダヘリシャイカ・サレム・アル・ダヘリの記事を見る
-
 元整形外科医/農園主散木洞人
元整形外科医/農園主散木洞人散木洞人の記事を見る
-
 豊橋技術科学大学パク ミンジョン
豊橋技術科学大学パク ミンジョンパク ミンジョンの記事を見る
-
 生理革命委員会澤田まりあ、山形萌花、山領珊南
生理革命委員会澤田まりあ、山形萌花、山領珊南澤田まりあ、山形萌花、山領珊南の記事を見る
-
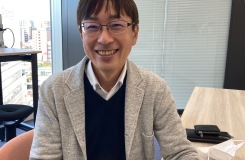 SOMPOケア株式会社藤田 定司
SOMPOケア株式会社藤田 定司藤田 定司の記事を見る
-
 おかやま山陽高等学校橘 里香サニヤ
おかやま山陽高等学校橘 里香サニヤ橘 里香サニヤの記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員坂入 悦子
ソシエタス総合研究所 研究員坂入 悦子坂入 悦子の記事を見る
-
 Hiro山下行政書士国際法務事務所 代表山下裕司
Hiro山下行政書士国際法務事務所 代表山下裕司山下裕司の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員Niklas Holzapfel ホルツ アッペル ニクラス
ソシエタス総合研究所 研究員Niklas Holzapfel ホルツ アッペル ニクラスNiklas Holzapfel ホルツ アッペル ニクラスの記事を見る
-
 サウンドエンジニアEmre・Ekici エムレ・エキジ
サウンドエンジニアEmre・Ekici エムレ・エキジEmre・Ekici エムレ・エキジの記事を見る
-
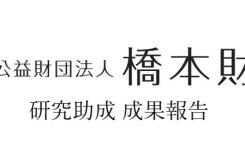 NPO法人岡山県国際団体協議会
NPO法人岡山県国際団体協議会岡山県国際団体協議会の記事を見る
-
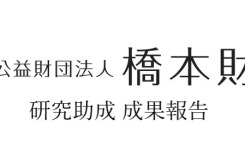 岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域 教授東條 光彦
岡山大学 学術研究院 社会文化科学学域 教授東條 光彦東條 光彦の記事を見る
-
 福岡大学 名誉教授田村 和夫
福岡大学 名誉教授田村 和夫田村 和夫の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員相川 真穂
ソシエタス総合研究所 研究員相川 真穂相川 真穂の記事を見る
-
 一般社団法人京都総合科学研究所 アドバイザー松村 道郎
一般社団法人京都総合科学研究所 アドバイザー松村 道郎松村 道郎の記事を見る
-
 ワラム株式会社 代表取締役加藤 侑子
ワラム株式会社 代表取締役加藤 侑子加藤 侑子の記事を見る
-
 岡山市立操南中学校 教諭/NPO法人国際協力研究所・岡山代表理事竹島 潤
岡山市立操南中学校 教諭/NPO法人国際協力研究所・岡山代表理事竹島 潤竹島 潤の記事を見る
-
 新西横浜街の予防医療ケア研究室 保健師・看護師・元先端バイオ創薬ベンチャー取締役五十嵐 直敬
新西横浜街の予防医療ケア研究室 保健師・看護師・元先端バイオ創薬ベンチャー取締役五十嵐 直敬五十嵐 直敬の記事を見る
-
 共著橋本俊明・秋吉湖音
共著橋本俊明・秋吉湖音橋本俊明・秋吉湖音の記事を見る
-
 ライター菊池 洋勝
ライター菊池 洋勝菊池 洋勝の記事を見る
-
 大東文化大学国際関係学部・特任教授 高崎経済大学経済学部・非常勤講師 目白大学経営学部経営学科&目白大学大学院経営学研究科 非常勤講師 長崎県佐世保市役所 経済活性化~産業振興に関するアドバイザー、博士(経済学)江崎 康弘
大東文化大学国際関係学部・特任教授 高崎経済大学経済学部・非常勤講師 目白大学経営学部経営学科&目白大学大学院経営学研究科 非常勤講師 長崎県佐世保市役所 経済活性化~産業振興に関するアドバイザー、博士(経済学)江崎 康弘江崎 康弘の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員秋吉 湖音
ソシエタス総合研究所 研究員秋吉 湖音秋吉 湖音の記事を見る
-
 JICA専門家足立 伸也
JICA専門家足立 伸也足立 伸也の記事を見る
-
 富士通株式会社 第三ファイナンス事業本部 シニアマネージャー安留 義孝
富士通株式会社 第三ファイナンス事業本部 シニアマネージャー安留 義孝安留 義孝の記事を見る
-
 EDAS(イーダス)理事長田村 拓
EDAS(イーダス)理事長田村 拓田村 拓の記事を見る
-
 監督・プロデューサー湯浅 典子
監督・プロデューサー湯浅 典子湯浅 典子の記事を見る
-
 日本経済大学 准教授山下 誠矢
日本経済大学 准教授山下 誠矢山下 誠矢の記事を見る
-
 人と医療の研究室 代表池尻 達紀
人と医療の研究室 代表池尻 達紀池尻 達紀の記事を見る
-
 一般社団法人飛島学園 代表理事堂野 博之
一般社団法人飛島学園 代表理事堂野 博之堂野 博之の記事を見る
-
 ニッセイ基礎研究所 生活研究部 主任研究員、ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任金 明中
ニッセイ基礎研究所 生活研究部 主任研究員、ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任金 明中金 明中の記事を見る
-
 医療法人財団足立病院 理事長、社会福祉法人あだち福祉会 理事長畑山 博
医療法人財団足立病院 理事長、社会福祉法人あだち福祉会 理事長畑山 博畑山 博の記事を見る
-
 教育研究家、合同会社ライフ&ワーク代表妹尾 昌俊
教育研究家、合同会社ライフ&ワーク代表妹尾 昌俊妹尾 昌俊の記事を見る
-
 ハーバード大学ベス・イスラエル・ディーコネス・メディカルセンター、高度消化管/最小侵襲外科フェロー中元 啓太郎
ハーバード大学ベス・イスラエル・ディーコネス・メディカルセンター、高度消化管/最小侵襲外科フェロー中元 啓太郎中元 啓太郎の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 主任研究員井上 登紀子
ソシエタス総合研究所 主任研究員井上 登紀子井上 登紀子の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員松田 郁乃
ソシエタス総合研究所 研究員松田 郁乃松田 郁乃の記事を見る
-
 ソシエタス総合研究所 研究員アイシェ・ウルグン・ソゼン Ayse Ilgin Sozen
ソシエタス総合研究所 研究員アイシェ・ウルグン・ソゼン Ayse Ilgin Sozenアイシェ・ウルグン・ソゼン Ayse Ilgin Sozenの記事を見る
-
 NPO法人岡山市子どもセンター 事務局久川 春菜
NPO法人岡山市子どもセンター 事務局久川 春菜久川 春菜の記事を見る
-
 ユースワーカー(Youth Woker)森分 志学
ユースワーカー(Youth Woker)森分 志学森分 志学の記事を見る
-
 ペンネーム三村 喜久雄
ペンネーム三村 喜久雄三村 喜久雄の記事を見る
-
 ペンネーム黒木 洋一郎
ペンネーム黒木 洋一郎黒木 洋一郎の記事を見る
-
 NPO法人チャリティーサンタ 理事河津 泉
NPO法人チャリティーサンタ 理事河津 泉河津 泉の記事を見る
-
 金沢大学人間社会学域地域創造学類・准教授 、特定非営利活動法人国土利用再編研究所・理事長林 直樹
金沢大学人間社会学域地域創造学類・准教授 、特定非営利活動法人国土利用再編研究所・理事長林 直樹林 直樹の記事を見る
-
 認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ理事長安藤希代子
認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ理事長安藤希代子安藤希代子の記事を見る
-
 カリフォルニア大学サンフランシスコ校小児胸部心臓外科教授佐野俊二
カリフォルニア大学サンフランシスコ校小児胸部心臓外科教授佐野俊二佐野俊二の記事を見る
-
 社会福祉法人 旭川荘 ひらたえがお保育園 園長江田 加代子
社会福祉法人 旭川荘 ひらたえがお保育園 園長江田 加代子江田 加代子の記事を見る
-
 NPO法人 おかやまUFE 副理事長 ・NPO法人 おかやまUFE 事務局阪井 ひとみ・永松千恵
NPO法人 おかやまUFE 副理事長 ・NPO法人 おかやまUFE 事務局阪井 ひとみ・永松千恵阪井 ひとみ・永松千恵 の記事を見る
-
 社会学者 東京大学名誉教授 認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長 上野 千鶴子
社会学者 東京大学名誉教授 認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長 上野 千鶴子上野 千鶴子 の記事を見る
-
 外務省 国際保健政策室長 鷲見 学
外務省 国際保健政策室長 鷲見 学鷲見 学の記事を見る
-
 プロ・アダプティブ・サーファー藤原(旧姓:川上)智貴
プロ・アダプティブ・サーファー藤原(旧姓:川上)智貴藤原(旧姓:川上)智貴の記事を見る
-
 京都大学霊長類研究所 教授正高信男
京都大学霊長類研究所 教授正高信男正高信男の記事を見る
-
 社会医療法人石川記念会HITO病院緩和ケア内科統括部長大坂巌
社会医療法人石川記念会HITO病院緩和ケア内科統括部長大坂巌大坂巌の記事を見る
-
 東京医療学院大学保健医療学部教授上田 諭
東京医療学院大学保健医療学部教授上田 諭上田 諭の記事を見る
-
 「夢を叶える145」ライター宮村孝博
「夢を叶える145」ライター宮村孝博宮村孝博の記事を見る
-
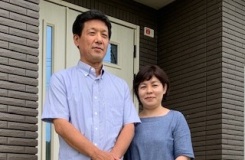 NPO法人 Anneの家 代表 美作地区里親会会員松本芳也・淳子夫妻
NPO法人 Anneの家 代表 美作地区里親会会員松本芳也・淳子夫妻松本芳也・淳子夫妻の記事を見る
-
 特定非営利活動法人あかね 代表理事中山 遼
特定非営利活動法人あかね 代表理事中山 遼中山 遼の記事を見る
-
 大阪市立総合医療センター 緩和医療科部長 兼 緩和ケアセンター長 大阪市立大学医学部臨床准教授 一般社団法人「こどものホスピスプロジェクト」常務理事 日本小児科学会専門医 英国カーディフ大学緩和ケア認定医(Certificate in Palliative Care) 日本緩和医療学会暫定多田羅竜平
大阪市立総合医療センター 緩和医療科部長 兼 緩和ケアセンター長 大阪市立大学医学部臨床准教授 一般社団法人「こどものホスピスプロジェクト」常務理事 日本小児科学会専門医 英国カーディフ大学緩和ケア認定医(Certificate in Palliative Care) 日本緩和医療学会暫定多田羅竜平多田羅竜平の記事を見る
-
 NPO法人 岡山マインド「こころ」/代表理事 一般社団法人お互いさま・まびラボ/副代表理事多田伸志
NPO法人 岡山マインド「こころ」/代表理事 一般社団法人お互いさま・まびラボ/副代表理事多田伸志多田伸志の記事を見る
-
 一般社団法人MY TREE代表理事 MY TREEペアレンツ・プログラムスーパーバイザー 認定フェミニストカウンセラー (公認心理師)中川和子
一般社団法人MY TREE代表理事 MY TREEペアレンツ・プログラムスーパーバイザー 認定フェミニストカウンセラー (公認心理師)中川和子中川和子の記事を見る
-
 兵庫県立ひょうごこころの医療センター精神科医師小田 陽彦
兵庫県立ひょうごこころの医療センター精神科医師小田 陽彦小田 陽彦の記事を見る
-
 独立行政法人国立病院機構福山医療センター院長岩垣博己・堀井城一朗・矢野 平
独立行政法人国立病院機構福山医療センター院長岩垣博己・堀井城一朗・矢野 平岩垣博己・堀井城一朗・矢野 平の記事を見る
-
 岡山大学 教授 文学部長田中 共子
岡山大学 教授 文学部長田中 共子田中 共子の記事を見る
-
 Civil Engineer (仕組みつくりの技術者)石田篤史
Civil Engineer (仕組みつくりの技術者)石田篤史石田篤史の記事を見る
-
 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹・経済学博士松山幸弘
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹・経済学博士松山幸弘松山幸弘の記事を見る
-
 岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター ART教育研究部門長・教授舟橋 弘晃
岡山大学生殖補助医療技術教育研究センター ART教育研究部門長・教授舟橋 弘晃舟橋 弘晃の記事を見る
-
 医療法人サンズ理事長浅野 直
医療法人サンズ理事長浅野 直浅野 直の記事を見る
-
 株式会社ヘリオス 代表執行役社長CEO鍵本忠尚
株式会社ヘリオス 代表執行役社長CEO鍵本忠尚鍵本忠尚の記事を見る
-
 慶應義塾大学文学部人間科学専攻教授(医療人類学) McGill大学人類学部・医療社会研究学部Ph.D.北中淳子
慶應義塾大学文学部人間科学専攻教授(医療人類学) McGill大学人類学部・医療社会研究学部Ph.D.北中淳子北中淳子の記事を見る
-
 岡山大学病院 緩和支持医療科片山英樹
岡山大学病院 緩和支持医療科片山英樹片山英樹の記事を見る
-
 岡山市役所 保健福祉企画総務課松岡克朗
岡山市役所 保健福祉企画総務課松岡克朗松岡克朗の記事を見る
-
 近現代史研究家青木康嘉
近現代史研究家青木康嘉青木康嘉の記事を見る
-
 独立行政法人国立病院機構福山医療センター院長岩垣博己・長谷川利路・中島正勝
独立行政法人国立病院機構福山医療センター院長岩垣博己・長谷川利路・中島正勝岩垣博己・長谷川利路・中島正勝の記事を見る
-
 岡山高等学院 副校長 水野文一郎
岡山高等学院 副校長 水野文一郎水野文一郎の記事を見る
-
 社会の仕組み屋、社会の編集者石原 達也
社会の仕組み屋、社会の編集者石原 達也石原 達也の記事を見る
-
 一般社団法人SGSG理事長/中国学園大学子ども学部講師野村泰介
一般社団法人SGSG理事長/中国学園大学子ども学部講師野村泰介野村泰介の記事を見る
-
 一橋大学経済研究所 教授神林 龍
一橋大学経済研究所 教授神林 龍神林 龍の記事を見る
-
 特定医療法人自由会 理事 (社会福祉法人敬友会 理事、公益財団法人橋本財団 理事)橋本 健二
特定医療法人自由会 理事 (社会福祉法人敬友会 理事、公益財団法人橋本財団 理事)橋本 健二橋本 健二の記事を見る
-
 医療法人社団 岡山二人クリニック 理事長、医学博士林 伸旨
医療法人社団 岡山二人クリニック 理事長、医学博士林 伸旨林 伸旨の記事を見る
-
 フリーライター渡辺嗣郎(わたなべ しろう)
フリーライター渡辺嗣郎(わたなべ しろう)渡辺嗣郎(わたなべ しろう)の記事を見る
-
 国立大学法人岡山大学 副理事(国際担当)横井 篤文
国立大学法人岡山大学 副理事(国際担当)横井 篤文横井 篤文の記事を見る
-
 ペンネームドクターX
ペンネームドクターXドクターXの記事を見る
-
 NPO法人 山村エンタープライズ 代表理事藤井裕也
NPO法人 山村エンタープライズ 代表理事藤井裕也藤井裕也の記事を見る
-
 キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長桜井 なおみ
キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長桜井 なおみ桜井 なおみの記事を見る
-
 AMDA(アムダ) グループ代表・認定非営利活動法人AMDA 理事長菅波 茂
AMDA(アムダ) グループ代表・認定非営利活動法人AMDA 理事長菅波 茂菅波 茂の記事を見る
-
 ふれあい歯科ごとう代表五島 朋幸
ふれあい歯科ごとう代表五島 朋幸五島 朋幸の記事を見る
-
 介護従事者髙田 浩一
介護従事者髙田 浩一髙田 浩一の記事を見る
-
 ケアマネ-ジャー・社会福祉士かえる ちから
ケアマネ-ジャー・社会福祉士かえる ちからかえる ちからの記事を見る
-
 五常・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役社長慎 泰俊
五常・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役社長慎 泰俊慎 泰俊の記事を見る
-
 NPO法人 ポケットサポート代表理事三好 祐也
NPO法人 ポケットサポート代表理事三好 祐也三好 祐也の記事を見る
-
 医療法人 寺田病院 院長板野 聡
医療法人 寺田病院 院長板野 聡板野 聡の記事を見る
-
 鳥取市立病院 地域医療総合支援センター 生活支援室 副室長、リハビリテーション部 副部長、歯科 医長目黒 道生
鳥取市立病院 地域医療総合支援センター 生活支援室 副室長、リハビリテーション部 副部長、歯科 医長目黒 道生目黒 道生の記事を見る
-
 鳥取市立病院地域医療総合支援センター長 鳥取市福祉部参与足立 誠司
鳥取市立病院地域医療総合支援センター長 鳥取市福祉部参与足立 誠司足立 誠司の記事を見る
-
 ペンネーム池井戸 高志
ペンネーム池井戸 高志池井戸 高志の記事を見る
-
 ペンネーム池田 出水
ペンネーム池田 出水池田 出水の記事を見る
-
 岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科教授松岡 順治
岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科教授松岡 順治松岡 順治の記事を見る
-
 鳥取市立病院 名誉院長田中 紀章
鳥取市立病院 名誉院長田中 紀章田中 紀章の記事を見る
-
 岡山大学大学院保健学研究科 副研究科長 教授齋藤 信也
岡山大学大学院保健学研究科 副研究科長 教授齋藤 信也齋藤 信也の記事を見る
-
 公益財団法人橋本財団 理事長、医学博士橋本 俊明
公益財団法人橋本財団 理事長、医学博士橋本 俊明橋本 俊明の記事を見る